こんにちは✿
今日は「HSP」の提唱者である、エレイン・N・アーロン博士の本、『ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。』の概要と読んだ感想をブログにまとめようと思います。
- HSPの第一人者の本に興味がある
- この本のあらすじを知りたい
- この本のレビューを知りたい
HSPとは?
HSPは、Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)の略称です。なんだか病名のように聞こえるかもしれませんが、これは遺伝子的に生まれ持った気質のことで、アメリカの心理学者であるエレイン・N・アーロン博士が提唱した心理学的概念です。
生まれつき「非常に繊細な人」「敏感な人」「感受性が強い人」などという意味です。
全人口の約5人に1人はこのHSPに当てはまっているそうです。
HSPについてまとめた記事もあるので、興味がある方はぜひ。
HSPがポジティブになれる方法を著者が伝授

<タイトル>
ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。
<詳細>
- 著者:エレイン・N・アーロン著(1996年)
- 訳者:冨田香里訳(2000年)
- 出版社:講談社
- ページ総数:337ページ
<内容>
「タフさ」や「強さ」が重要視されるこの世の中で、「神経質」「内向的」など、繊細な人にはとても生きづらさを感じる。著者のエレイン・N・アーロン博士は、そんな繊細で敏感な人のマイナスのイメージを取り除き、繊細な人が自分と向き合い、ポジティブに生きれる方法をアドバイスする。また、アーロン博士の多くの人のインタビューによって見えてきたHighly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)、通称「HSP」の特徴についても詳しく書かれている。
HSPの提唱者が書いた信憑性がある本なのでおすすめします
著者のエレイン・N・アーロン博士は、HSPを提唱したいわば、HSPの第一人者です。
彼女は学者でもあり、長い年月をかけて様々な調査を行い、HSPの特徴をまとめたのが、この『ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。』という本です。
学者の本なので、学術論文でもあります。
ということは、かなり信憑性があるってことなんです!
- HSPのことをよく知れる
- 著者がHSPの第一人者
- 学者の目線で書かれているので信憑性がある
まさしく、
HSPのことを知るには、まずこの本から!
だと思います。
HSPのことをもっとよく知りたいので読みました
私がこの本を読もうと思った理由は、
HSPを自覚したらとても楽になったので、HSPのことをもっとよく知りたい!
と、思ったからです。
HSPを自覚する前は、自分の気にしすぎな性格に悩んでいましたが、HSPのことを知ってからは、原因がわかったからなのか、すごく楽になれました。
原因がわからないと、対処の仕方もわからないし、何より不安が募ります…。
なので、私は自分がもっと楽に生きれるために、HSPのことをよく知って、自分と向き合う方法を学ぼうと思ったのです。

自分をよく知るというのは、大事なことだもんね。
上記でも書きましたが、この本はHSPの第一人者の本なので、HSPのことを正しく知れるのはやはりこの本からだと思ったのが、この本を読もうと思ったきっかけです。
- 自分の気にしすぎな性格に悩む
↓ - HSPを自覚する
↓ - 原因がわかって楽になれた
↓ - HSPのことをもっとよく知りたい! ← 読もうと思った理由
HSPの特徴と辛いときの対処法が多く書かれている

この本の内容を一言で言うと、
「HSPを偏見で見るべきではない」
といった感じです。
HSPは、内気でどこか弱々しいというマイナスのイメージがあり、アーロン博士は「なんたることだ!」言わんばかりに、世間のHSPのマイナスイメージを否定しています。
本の内容は他にも、以下のことがありました。
- HSPの特徴
- 自己診断テスト
- 様々なHSPの過去の話(辛い経験など)
- 子ども時代と思春期の重要性
- HSPの社会生活について
- HSPの仕事について
- HSPの恋愛と友情について
- HSPと医者と薬
- HSPとスピリチュアルな話
自己診断テストは本を引用して記事にしてあります。
すぐにテストできるので、興味のある方はぜひ。
アーロン博士のHSPの分析が秀逸
ここからは、本を読んだ感想を書いていきます。
- HSPはブレーキをかける相談役
- 有能だが対人恐怖で昇進が見込めなかったパウラさんの話
- HSPのカラダをケアすること=乳幼児の世話をすること
- HSPのレッテルを言い訳にばかり使わない
HSPはブレーキをかける相談役

まず、私が印象に残ったのは、
HSPはブレーキをかける相談役
ということです。
アーロン博士は、第一章のP.54~で騎馬民族の話をしました。
要約して書くと、以下の通りです。
約7000年前の騎馬民族が勢力を拡大し、社会を支配していたその中で、戦う戦士たちの他に、僧や判事のように「止まりなさい」「ちょっと考えなさい」というブレーキをかける相談役が必要だった。
アーロン博士は、まさしくこの相談役こそが、HSPの役割ではないかと言っています。
HSPはこの相談役になる傾向がある。
ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。 P.55
これは、私もすごく共感できました!
HSPの特徴として、
- 色々なことを考え、先のことを見通す
- 相手に寄り添うことができる
というのを考えれば、「HSPは相談役に向いている」というのは納得いきますよね。
まさしく、縁の下の力持ちですね!
そしてアーロン博士は、戦士なり相談役なり、それぞれのスタイルにしっかり価値を見出すことが重要だとも言っています。
時にはイヤがられながらも、大勢の人が暴走する歯止め役を果たす。私たちは自分たちの役目を果たすためにも、自信を持たなければならない。戦士たちのスタイルはそれとして価値がある。しかし、私たちのスタイルにも大いに価値があるのだ。
ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。 P.56
こういう「どんな個性でも自信を持とう!」と言っているアーロン博士を、とてもかっこよく思いました!
そして、学者なだけあってか例えもわかりやすいです。
世間の風潮では、攻撃的、強さ、タフさなどが重要視されていて、HSPの個性は、世間のイメージで「価値が薄い」ものとされていますが、それを真っ向から否定し、誰にでも価値があると堂々と言えるアーロン博士は、本当にかっこいい!
同じ女性として、憧れますね!
有能だが対人恐怖で昇進が見込めなかったパウラさんの話

アーロン博士は、様々な人へ以下のことを繰り返し行ってきました。
- インタビュー
- 電話調査
- HSP観察
- 講座
- 会話
- 個人相談
- HSPとの心理療法
このような調査で最終的に対象となったHSPの数は数千人もいたそうです。

何人もの調査でHSPというものが見えてきたんだね!
その経験から基づいているので、やはりこの本で書いてあるHSPの特徴や心のケア方法などはかなり信憑性があると言えますね!
アーロン博士がインタビューしたHSPの中には、
- 学校で人気者だったが、新しい学校ではいじめの標的にされたという男性
- 貧しい家に生まれ、小さい頃から兄たちから性的ないたずらを受けたという女性
- 結婚生活の不満を両親から聞かされていたという女性
など、辛い過去を持つ人もいたそうです。
私がその中でも、
結婚生活の不満を両親から聞かされていたという女性(以下、パウラさん)
が、印象に残りました。
そのパウラさんが、アーロン博士のインタビューを受けたときの話(P.175)をまとめると、以下の通りです。
- 30代の女性
- 生まれつき敏感で恥ずかしがり屋
- イベントの裏方を取り仕切る仕事をしていた
- 有能だったが、人前でのスピーチや人づきあいが苦手なため、昇進できなかった
- 対人恐怖を克服するためたくさんの努力した
なぜパウラさんは対人恐怖なのか?
アーロン博士は、パウラさんの子ども時代に原因があるだろうと言っています。
本のP.176にパウラさんの子ども時代のことが書かれています。
要約すると、以下の通りです。
※少々過激かもしれないので、苦手な方は注意してください。
パウラさんの父親は賢く分析的な人で、パウラさんをとても可愛がっていた。しかし、彼は「怒り依存症」で、パウラさんの可愛がり方も性的なものも混じっていた。
一方、母親はまわりの目をとても気にする人で、意志の強い夫に頼り切りだった。その上、子育てを嫌い、出産の大変さ、赤ん坊が可愛くないという話をパウラさんにしていた。
さらに、パウラさんが少し大きくなる頃には、母親がパウラさんをカウンセラーに仕立て、「性生活がいかに嫌いか」など、子どもには無理がある話をしていた。
出産や性生活の話なんて子どもには荷が重すぎますね。
その両親には少し憤りを感じてしまいます…。
アーロン博士は、本の各所で、子ども時代の他者からの愛情の重要性を話しています。
安心できるアタッチメントを感じて育ったHSPは、自分の中に「心の資源」があり、刺激過多の状況に出くわしてもうまく切り抜けることができるようになると言える。
ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。 P.94
パウラさんが、人前でのスピーチや人づきあいが苦手になってしまったのも、この母親の不安定なアタッチメント(愛情)が原因だろうと、アーロン博士は分析しています。
なんとも辛い経験をしてきたパウラさん…。
ここからは、私が印象に残った理由を書きます。
- 自分と同じ性別で年代も一緒
- 精神的な虐待を受けて育った
- 自分の苦手なことを克服しようと一生懸命努力した
パウラさんは、インタビュー当時の年代になってしまいますが、30代の女性。
私も同じなので、すごく親近感がありました。
そして、私はパウラさんの子ども時代を「精神的な虐待」のように感じ、考えさせられえる部分があったのです。
私は、アーロン博士が言っている、
「子ども時代の安定した愛情」
というのに、ものすごく共感しています。
私は、それが子どもの教育で一番大事なことだと思っているので、それを味わえなかったパウラさんのことを思うと少し悲しい気持ちになります。(HSP特有の感情移入です)

でも、パウラさんはそれを乗り越えようと努力しているんだよね。
そうなんです。
パウラさんは、自身の対人恐怖を克服するために、たくさんの本を読み、一生懸命努力したそうなんです。
しかし、それだけでは効果は上がらず、長期の集中的なセラピーも受けたそうです。
私は、自分を変えようと努力するパウラさんは偉いなと思いました。
それも印象に残った理由です。
きっと今もどこかで頑張っているのかな。
頑張れ、パウラさん!
HSPのカラダをケアすること=乳幼児の世話をすること

アーロン博士は、本の第三章で、
HSPの敏感すぎるカラダをケアすることの大切さ
を語っていて、さらに、
HSPのカラダをケアすることは、乳幼児の世話をすること
とよく似ていると言っていました。
HSPのカラダと乳幼児の共通点は、
- 神経が適度に高ぶる
- 疲労していると言うことをきかなくなる
- 何かトラブルが起きても言葉で訴えることができない
と、ありました。
これは、ほほぁーと思いました。
そういう例えがあったかと!
つまり、生まれて間もない乳幼児は、刺激に対応する術を持っておらず、それゆえに敏感になってしまう。HSPのカラダも、同じではないか?ということですよね!(解釈合ってるかな…)

確かにHSPの特性って赤ちゃんのようにデリケートだよね。
乳幼児と言うと、大げさに聞こえるかもしれませんが、大げさなのがHSPの性なのです(笑)
そして、アーロン博士は、
自身のカラダを乳幼児のように扱い、自分の親になるイメージでいること
を語っています。
あなたのカラダを乳幼児として扱うこと。自分のカラダを見守る親(養育者)になること。
ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。 P.92
さらに、自分自身の親になる=自分のカラダをケアする(第四章では「再教育する」という言葉も使っています)具体的な心理作戦も挙げてくれています。
例えば、以下のような神経が高ぶる状況のとき対処法です。(文章は少々変えています)
都会の大きな駅で人混みに圧倒され、恐怖を感じたとき。
⇓
- 状況をリフレーミング(組み立て直し)する
今まで同じような状況でうまく対処できたかを思い出す。 - あなたの心を落ち着かせるおなじないの言葉や祈りの言葉、マントラなどを繰り返す。それを毎日練習しておくこと
これをしてかえって神経が高ぶるならすぐにやめる。うまくいかないことで気を落とすことはない。そのフレーズによって少しは落ち着くはずだから。 - 自分の神経の高ぶりをよく観察する
自分をそばで見つめるもう一人の自分をイメージし、その人に自分の様子を話させてみる。「ほら、またよ。動揺しているのね。とりあえずちょっと休めば大丈夫よ。」と。 - その状況を好ましく思う。さもなければ、自分の神経の高ぶりを好ましく思うようにする
ばかばかしく聞こえるかもしれないが、大切なこと。オープンな愛情深い意識というのは、きつく締め付けられ、神経が高ぶりすぎている意識の対極にある。たとえその状況を好ましく思えなくても、そういう自分を好ましく思うことが、きわめて重要。
いかがですか。
完璧にできるにはハードルが高そうですが、どれも今日からできることばかりですよね!
実は、「おまじないの言葉」や「自分を観察する」などは、私が日頃から意識していることだったりします!
何だか自分のやり方が思わぬ正解だったように思えて嬉しくなりました(笑)
他にも、「物理作戦(P.114~)」もありましたが、長くなるので割愛しますね。
興味がある方は、ぜひお手に取ってご自身で読んでみてください(^^)
HSPのレッテルを言い訳にばかり使わない

これは、本書ではなく訳者のあとがきについてです。
たった3ページのあとがきでしたが、私は印象に残ったことがありました。
「私は弱い」と思ってしまえば、それが言い訳になって終わってしまう。けれど「自分はHSPだ」と思えば、どこにどう気を付ければいいか具体的に見えてきます。ただ、HSPという新たなレッテルに頼るとしたら、これまたよくない。
ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。(訳者あとがき) P.336
このあとに訳者は、
何かしらのレッテルは、自分を見つめ直すはずのもので、「私は○○だから」という言い訳するためのレッテルにすり替わっている
ということを嘆いていました。
これは、私もすごく共感しました。
なぜかというと、実際、私の周りにも「○○だから」と言って何もせず、言い訳ばかりしている人がいたのです。

確かに辛いときの言い訳で使うのはアリだと思うけど、それにばかり頼るのも少し違う気がするよね。
私は、HSPというのを自覚したとき、
このレッテルは自分を守るもので、何もしない言い訳には使わないでおこう
と心に誓いました。
私は、HSPを自覚したらとても楽になれたので、このHSPというレッテルの使い方を誤ってはいけないと思ったのです!
HSPを知るのは、終わりではなく、始まりだ
と、まさしく私が感じていたことを訳者は言っていて、かなり共感できました!
まとめ:少し難しいがHSPが読んで損はない本
というわけで、『ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。』の感想をこのブログにまとめてみました。
正直、学者の本なだけあって、
少し難しい!
と、思ったのも率直な感想です(^^;)
本から何年も離れていた私には、少しハードルが高くもありましたが、でもHSPの特徴や様々な人のエピソードが知れたので、結果的に読んでよかったです。
私みたいに本から離れていた人にとって、学術的な本の337ページというのは、少しためらいがあるかと思いますが、HSPの人は読む価値があると思います!
ぜひ、お手に取ってみてください!
ここまでブログを読んでくれてありがとうございます。
それでは✿
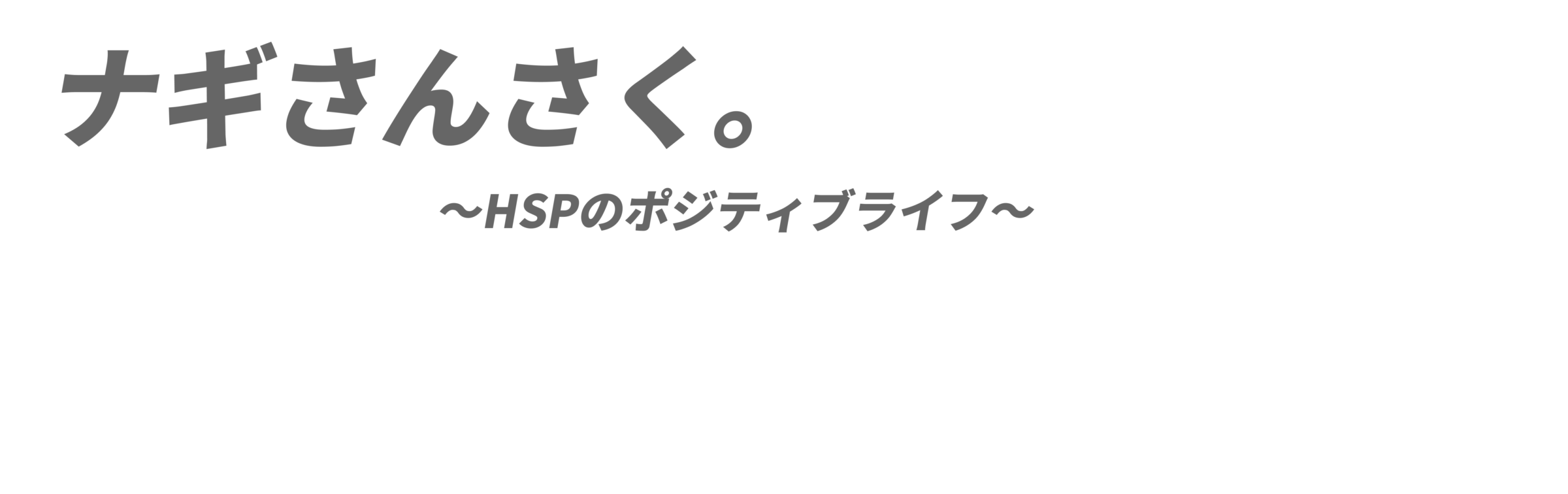
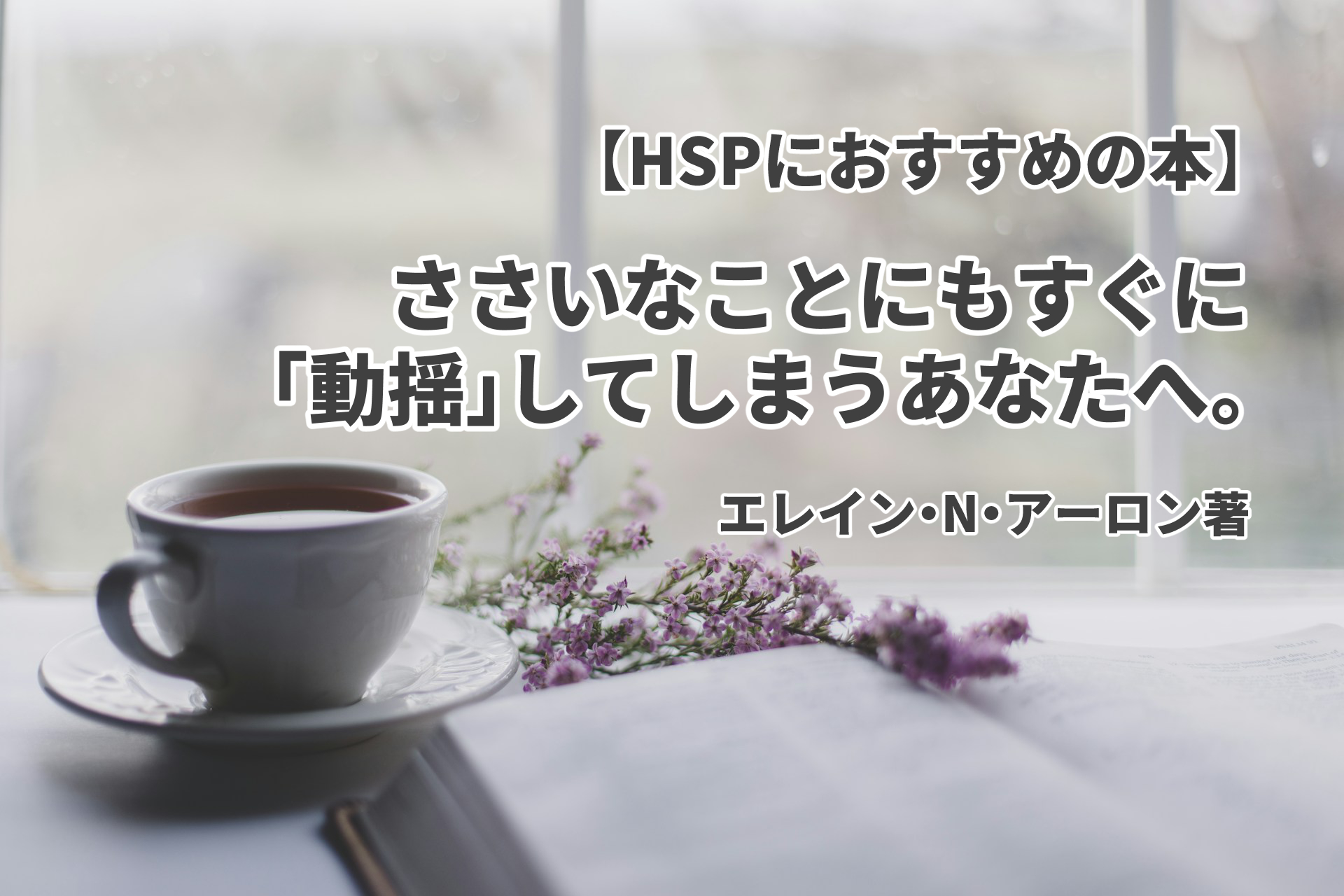






コメント