こんにちは✿
また新たに本を読みました。
三谷はるよさんの「ACEサバイバー 子ども期の逆境に苦しむ人々」という本です。
著者の三谷はるよさんは、龍谷大学社会学部の准教授で、福祉・家族・子どもに関する問題について研究しています。
この本を簡単に言うと、子どもの頃のトラウマ体験についてまとめた本です。
今日は、その本を感想を書いていきます。
- 子どもの頃のトラウマ体験の本を探している
- 子どもの頃のトラウマ体験について詳しく知りたい
- トラウマ体験を克服したい
本の概要

<タイトル>
ACEサバイバー 子ども期の逆境に苦しむ人々
<詳細>
- 著者:三谷はるよ
- 出版社:筑摩書房
- ページ総数:272ページ
<内容>
虐待、ネグレクト、家族の問題などACE(子ども期の逆境体験)は、その後の人生に大きく影響し、生きていくのが困難になるという研究がある。ACEはその人の心身にどのような影響を与えるのか、ACEサバイバーが語る壮絶な体験談など、これまで注目されなかったACEの実態が明らかになってきている。ACEの調査データに基づいて、ACEサバイバーが抱える生きづらさを解決する方法や社会的に不利にならない方法なども考える。
読もうと思った理由

この本を読もうと思った理由なのですが、私はよく「生きづらさ」について考えることが多いです。
生きづらさを感じる原因は、
- 生まれ持った気質(HSPなど)
- 病気や障害を抱えている
- 社会情勢
などがあると思います。
しかし、この本でもあるように「子どもの頃のトラウマ」というのも生きづらさにすごく関係があるように感じました。
生きづらさって心の問題が大きく影響していて、
「子どもの頃のトラウマ → 心の傷を抱える → 生きづらい」
という負の連鎖になっているのではと思います。
私は子どもの頃にとてつもない虐待を受けたというわけではないですが、心の在り方や心の問題について重要視するタイプなので、この本に興味が湧きました。
本の感想

ここからは、本の感想です。
ACEの解説も含めて書いていきます。
調査データを基にACEのことを解説
そもそも「ACE」とは何の略なのでしょうか。
本書によると、
ACE(=Adverse Childhood Experience)の略で、日本語で言うと「子ども期の逆境体験」
と言うそうです。
さらに、そのACEの過去を抱えて生きている人たちを「ACEサバイバー」と言うそうです。
子ども期の逆境体験とは、以下のようなものです。
- 身体的・精神的・性的虐待
- 身体的・心理的ネグレクト
- 親との別離
- 家族のアルコール・薬物依存 etc.
アメリカではこのACE研究が進んでおり、日本でもACEの大規模調査が京都大学で行われたそうです。
その調査によってわかったのは、ACEサバイバーの人は、そうでない人と比べて、
- 病気
- 精神疾患
- 中卒・高卒
- 貧困
- 離婚
などに陥る確率が高くなるそうです。

やはり心の傷があると生きにくくなってしまう印象を受けますね。
本書では、このような調査のデータなどが事細かく書かれています。
ACEサバイバーの壮絶な人生に驚愕
さらに本書では、著者の三谷はるよさんが直接インタビューしたACEサバイバーの壮絶な人生が書かれていました。
(やや過激な内容のため、詳しく言うのは控えます)
インタビューした2人のACEサバイバーの子ども期は、とにかく悲しく、虐待やネグレクトが日常の冷たい環境でした。

あまりにも壮絶で、読んでいて少ししんどくなりました。
そんなACEサバイバーは、その後の人生も困難の連続でした。
「心の傷は強く生きるために必要」という考えもあると思うのですが、このACEサバイバーのようにあまりにも逃げ場がない、心の支えがないなどの状況が続いてしまうと心が崩壊してしまうように思います。
私が何とか生きてこれているのは、まわりの支えなどがあったからで、それがなかったら今どうなっているのかと自分でも怖くなります。
ACEサバイバーが生きやすくなるには

子ども時代の一番多感で大事な時期に、大きなトラウマを持ってしまうと、今後の人生に大きく影響してしまうというのを本書から改めて学んだ気がします。
じゃあ、どうすることもできないのか?
という考えがよぎってしまいますが、本書ではACEサバイバーを救い、予防する方法の提案をしています。
ここで注目すべきは、人生の初期にACEによって受傷しながらも、その傷とうまく折り合いをつけて強く生きている人たちが存在するという事実です。そういう人々は、芸能人やスポーツ選手、政治家など有名人の場合もありますが、私たちが暮らす街の中ですれ違う、見た目には「ごく普通の人たち」である場合がほとんどです。
『ACEサバイバー 子ども期の逆境に苦しむ人々 P.126』
主な提案は、
- レジリエンス(逆境から回復する力)
- 子ども期の良い体験
- 社会のしくみの改善
などが効果的ではないかと書かれています。
本書では、「レジリエンス ー 人生の危機を乗り越えるための科学と10の処方箋」という著書で、レジリエンスを高める方法について書かれています。
- 楽観主義を育むこと
- 恐怖と向き合うこと
- 道徳指針を強化すること
- 信仰とスピリチュアリティの実践
- 社会的なサポートを受けることと与えること
- レジリエントなロールモデルを真似ること
- 身体的トレーニングをすること
- 精神的トレーニングをすること
- 認知・感情の柔軟性を高めること
- 生きる意味、目的、成長を見いだすこと
さらに、「子ども期の良い体験」は、文字通り子ども時代の良かった経験を指し、「子ども期の逆境体験」とは真逆の意味です。
逆境に苦しんでいた中でも、そこに自分が落ち着ける居場所があったり、心の支えがあった人は、成人後の精神的な問題が発生するリスクを軽減できることも調査によってわかったそうです。
レジリエンスと子ども期の良い体験、そして、社会がACEサバイバーを予防または対処するしくみを作ることが、ACEサバイバーが生きやすくなるための第一歩になるのではないかと、本書で解説しています。
まとめ:ACEの実態と解決法を提案してくれている本
私も子どもの頃の体験というのは、ものすごく重要だと考えるので、この本に共感できるところは多くありました。
昔はよく、「うつ病は甘えだ」などと心・精神を軽んじている考えがあった気がします。
しかし、今は多くの研究が進み、心の病気は普通の病気と同じで心身を蝕むことがわかってきていますし、心は目に見えないので傷を見逃しがちです。
この本でもあるように、もっと心を重要視し、みんなが生きやすい社会になってくれれば良いなと思いました。
というわけで、ここまで読んでくれてありがとうございます。
それでは✿
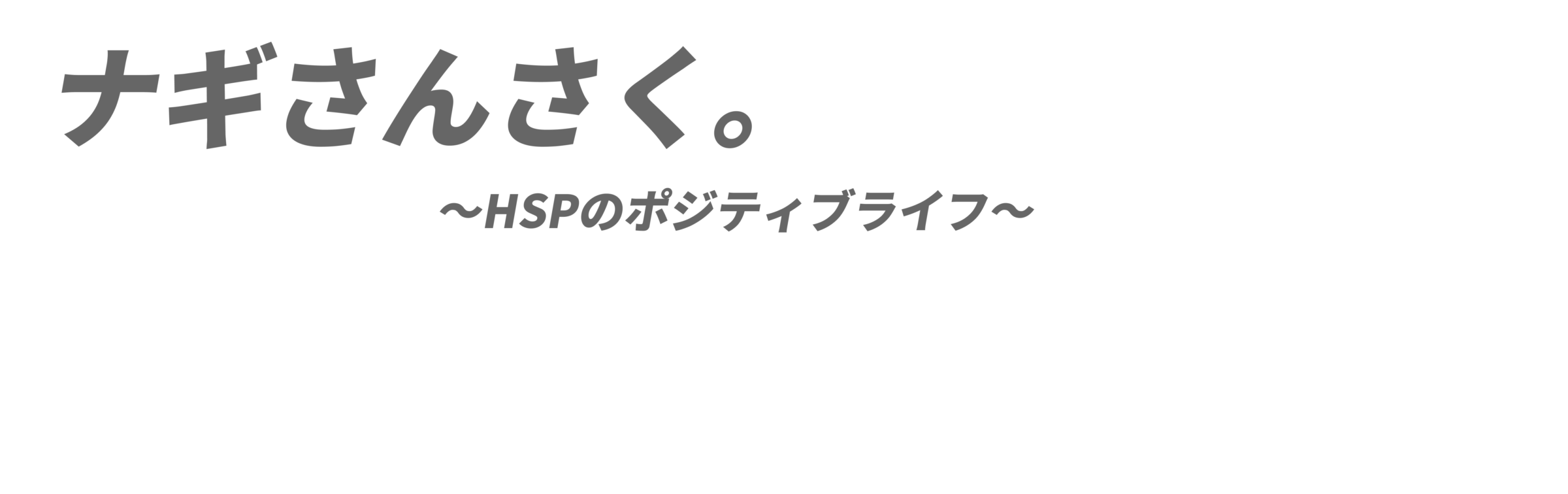


コメント