こんにちは✿
HSPは直観的な人が多いと言われているそうです。
「直感」ではなく「直観」ですよ(^^)
簡単に違いを言うと、
- 直感 → 物事を瞬時に捉える。勘。
- 直観 → 自分のこれまでの経験や知識を元に物事を捉える。
という感じです。
しかし、私は直観には様々な落とし穴があると思います。
というわけで、今日は、
- HSPが直観的に考えると起こりえること
- HSPが客観視して物事をとらえる方法
について考えてみました!
HSPとは?
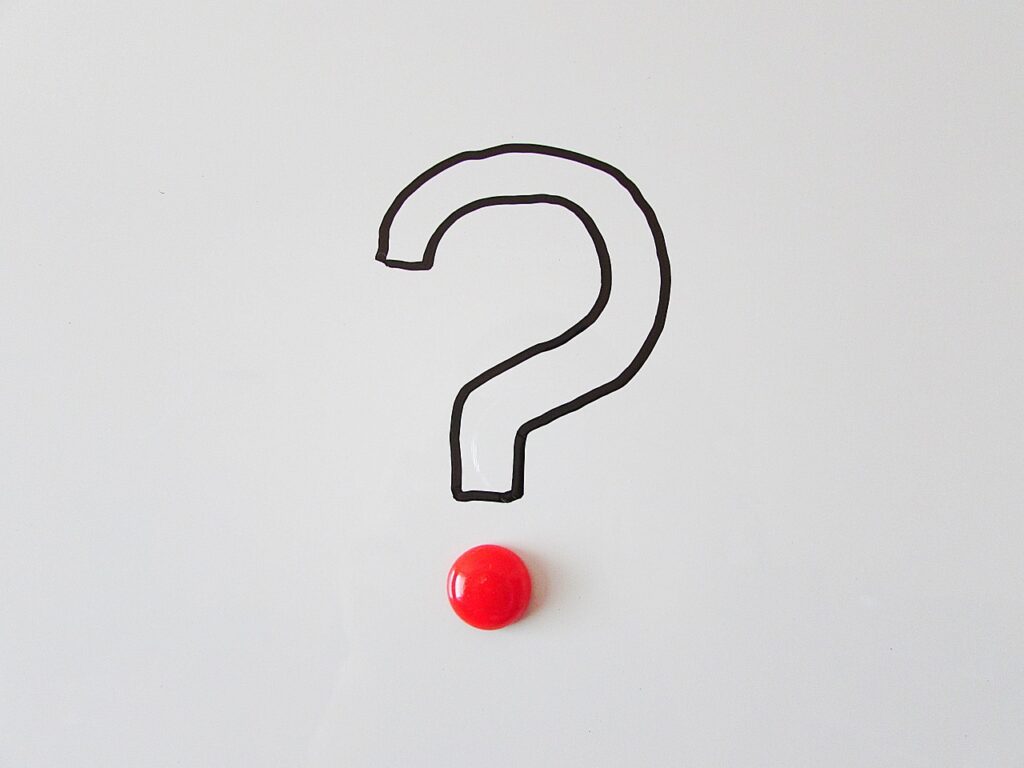
HSPは、Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)の略称です。なんだか病名のように聞こえるかもしれませんが、これは遺伝子的に生まれ持った気質のことで、アメリカの心理学者であるエレイン・N・アーロン博士が提唱した心理学的概念です。
生まれつき「非常に繊細な人」「敏感な人」「感受性が強い人」などという意味です。
全人口の約5人に1人はこのHSPに当てはまっているそうです。
HSPについてまとめた記事もあるので、興味がある方はぜひ。
HSP関連の本はこちらから。
そもそも「数字」って何?

○○の数字はどうだった?

数字上ではこうなっているね。
などと、普段から何気なく使っている「数字」という言葉ですが、
「数字」は「データ」を意味していることが多い
ということは知っていますか?
これは、「データ」ということばを知ると「数字」という言葉を理解できます。国際標準化機構の「ISO/IEC 2382-1」および日本工業規格の「X0001 情報処理用語-基本用語」において、いわゆる「ISO規格」において「データ」という言葉は、
“A reinterpretable representation of information in a formalized manner suitable for communication, interpretation, or processing.”「情報の表現であって、伝達、解釈または処理に適するように形式化され、再度情報として解釈できるもの」
Wikipedia – データ
と定義付けされています。うーん。説明が難しいですね(-ω-;)
平たく言うと、
- ラベリングされていない → 数字
- ラベリングされている → データ
です。具体的には、
●数字=単なる数の羅列
「1・2・3…」や「1個・2個・3個…」
●データ=数に意味があるもの
「値札が付いているりんご1個・2個・3個…」
ということです。データと言うと堅苦しく聞こえるので、この記事で私が書く「数字」というのは「データ」のことを指しています。「数字」ということばの方が一般的なのでそのように書いています。「データ」というと難しくなってしまうので(苦笑)
全てのHSPが数字を直観的に読み解くわけではない
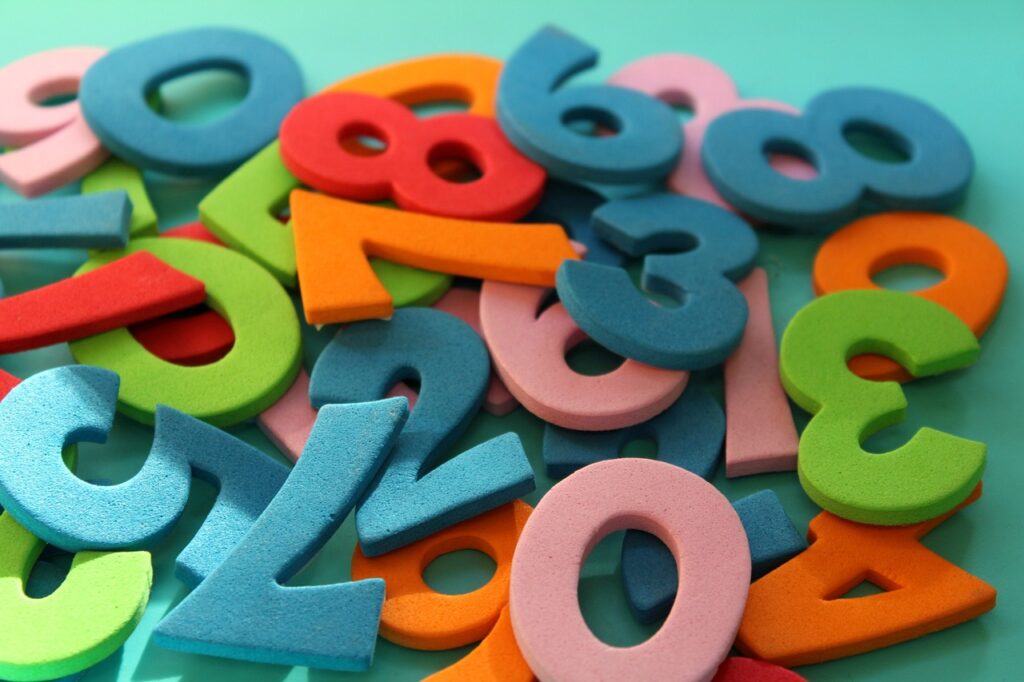
HSPは直観的な判断を好みます。
そのため、数字を読み解く際も直観的に受け取る傾向があると考えられますが、これには個人差があり、全てのHSPが必ずしも数字を直観的に受け取るわけではありません。

HSPの中には、数字を論理的に解析するスキルを持つ人もいて、直観と分析を組み合わせて判断するケースもあるよ。
ただし、何かの数字を見たときに感情的な反応を示すことで、その情報を直観的に理解しようとすることがあり、これは、HSPが情報を感情的に処理することを意味しています。
HSP研究の第一人者のアーロン博士の研究によれば、HSPは感情的な反応や直観を重視しがちで、数字のような具体的で論理的な情報も直観で受け取る傾向があるとされています。アーロン博士は、直観のことを、悪い意味ではなく優れた特技だと分析してくれています。
われわれは誰もがこの四つの「機能」―感覚、直観、思考、感情―の中で、特にすぐれたものをひとつ持っている。HSPにとっては、直観がそれである場合が多い。
ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。 P.320
詳しくは、先ほど紹介した著書を読んでみてくださいね(*^^*)
直観的に判断する傾向が強いHSPが起こしてしまうこと

例①:数字を見てすぐに反応する →「すぐに」
例えば、
●子どものテストの点数が予想よりも低かった場合
HSPの気質を持った親は、

私の子どもは学力が低いのではないか?
と直観的に考え、子どもの将来の学力に対して過度に悲観的な見方をしてしまうときがあります。
例②:数字を感情で捉えてしまう →「感情が先に」
例えば、
●子どもの成績が学校全体の平均よりも低いことが分かった場合
HSPの気質を持った親は、

子どもは学校の勉強についていけていないのではないか?
と考え、過剰な補習や家での勉強または学習塾通いを検討しようとします。
例③:喜怒哀楽を過度に表現する →「喜怒哀楽にのせて」
例えば、
●いろいろな角度から数字を見て検証した後、それでも子どものテストの点数は低いと判断した場合
HSPの気質を持った親は、

いろんな数字を見たけど、やっぱり私の子どもは学力が低いのではないか?
と過度に悲観的に解釈し、必要以上に厳しい学習計画を立ててしまいます。
- 数字を見て「すぐに」反応する
- 数字を「感情」で捉えてしまう
- 「喜怒哀楽」を過度に表現する
HSPはどのように客観視すべきなのか

過度にならない考え方ならば、考え方自体がおかしいわけではありません。出来事の後に考えるプロセスを少し修正するだけでいいと思います。
例①~③の考え方(親心)
「行動」を単独で見た場合は、何らおかしくありません。
「子どもの成績や将来を心配したり」、「子どもが学校の勉強についていけていないから、学習塾に通わせたり」するということは親心としては当然だと思います。
ですが、この場合、
起こったこと + その後の考え方 = 直感的
という風にみなされてしまいます。
具体例において、どのような部分が直観的であり、どのように考えたり行動すれば客観視できていたのかを私なりに考えてみます。
例①:「予想」の基準は?
具体的な点数で考えるために、
●予想の点数が「80点」
●結果の点数が「70点」
という数字にしてみます。
この例において、親は「80点 → 70点」としか見ていません。さらに、その前にもテストがあったとして、その点数を、
●予想の点数が「80点」
●結果の点数が「70点」
●前回の点数が「70点」
という場合にしてみます。
この現象を含めて連続して考えたところ、
「前回のテスト結果 → 予想点数 → 今回のテスト結果」=「70点 → 80点 → 70点」
となります。

予想よりも低いけど、前回のテスト結果と同じだわ。まあまあね。
と考えて、そこまで憂いたりしなかったかもしれません。
また、
●予想の点数が「80点」
●結果の点数が「70点」
●前回の点数が「80点」
●クラスの平均点が「60点」
という場合も考えてみます。
こうなると、親は、

予想点数よりも10点低い点数だったけど、クラスの平均点よりも10点も高くてすごいわ。
と考えるかもしれません。
結果が同じでも考え方が違ってくる可能性がありますよね。
大切なことは一度立ち止まって、客観的に数字のみを見ることだと思います。
【注意点】
※いろいろな角度から数字を見るための例として「数字を連続して考えたところ」という検証方法を挙げましたが、本来は適切ではありません。
※わかりにくくなるため「平均値」「中央値」の意味の違いは考慮していません。
例②:「全体」の範囲は?
例②も例①と同じような考えで説明できます。
●子どもの成績が学校全体の平均よりも低いことが分かった場合
●子ども通う学校が他校よりも優秀な学校だった場合
全ての学校が同じ難易度のテストを受けるものと仮定し、
- 子どもの学校全体のテストの平均 → 「70点」
- 他校Aの学校全体のテストの平均 → 「50点」
- 他校Bの学校全体のテストの平均 → 「55点」
- 子どものテスト結果→「60点」
だったとします。
この場合、親は、

私の子どもはうちの学校全体のテスト結果の平均よりは10点低かったけど、A学校やB学校の点数よりは高いわ。まあまあね。
と考えるかもしれません。
何度も言いますが、大切なことは、一度立ち止まって客観視することです。
例③:「喜怒哀楽」が行き過ぎではないか?
さきほどまでとは毛色が違いますね。ここでは感情が論点となります。
この例では、
●いろいろな角度から数字を見て検証した後に、どの数字も期待にそぐわなかった
とします。
自分の期待に反した場合、残念に思うのは当然です。
しかし、喜怒哀楽が行き過ぎてしまうと、まわりから変な目で見られると思います。

この例の主体は、「親」じゃなくて「子ども」だよ。
HSPの場合、「共感しすぎだよ。落ち着いてね。」と言われても、その感受性の高さから、感情がうまくコントロールできずに共感しすぎてしまいます。
共感しすぎのせいで、主体となる子どもよりも喜怒哀楽を外に出してしまうと、子どもに相当大きなプレッシャーを与えてしまいます。
「今、一番落ち込んでいるのは子ども」という視点で、HSP的な共感力を別のベクトルで表現するのが重要
だと思います。
まとめ:客観視を大切にし、喜怒哀楽を表現する方向に注意する
というわけで、「HSPと客観視」についてまとめました。
- 直感や感情だけで情報を受け取らないように注意する
- 客観的な視点を意識する
少しかたい内容だったですかね?(^^;)
しかし、普段の生活で「客観的に物事を見る」ことで、感情に左右されることがかなり減るかなと思い、このブログ記事を書きました。
HSPの直観は大切ですが、それに頼りすぎると物事の本質を見抜けないときがあるので、広い視野で物事を見るようにしましょう(*^^*)
ここまでブログを読んでくれてありがとうございます。
それでは✿
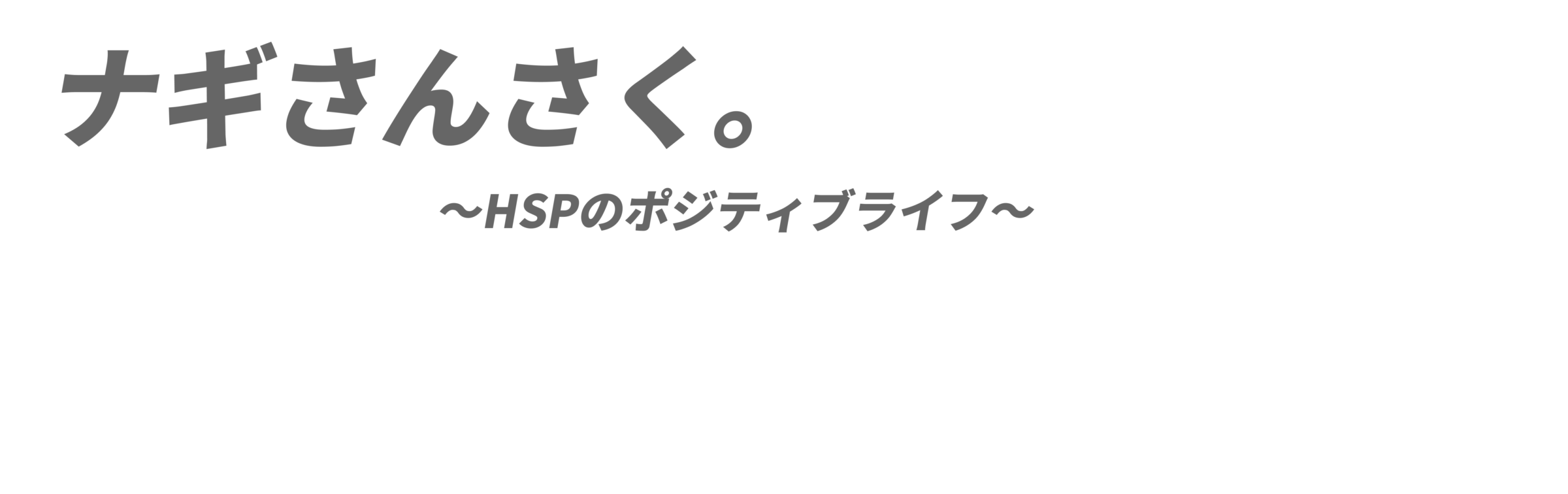
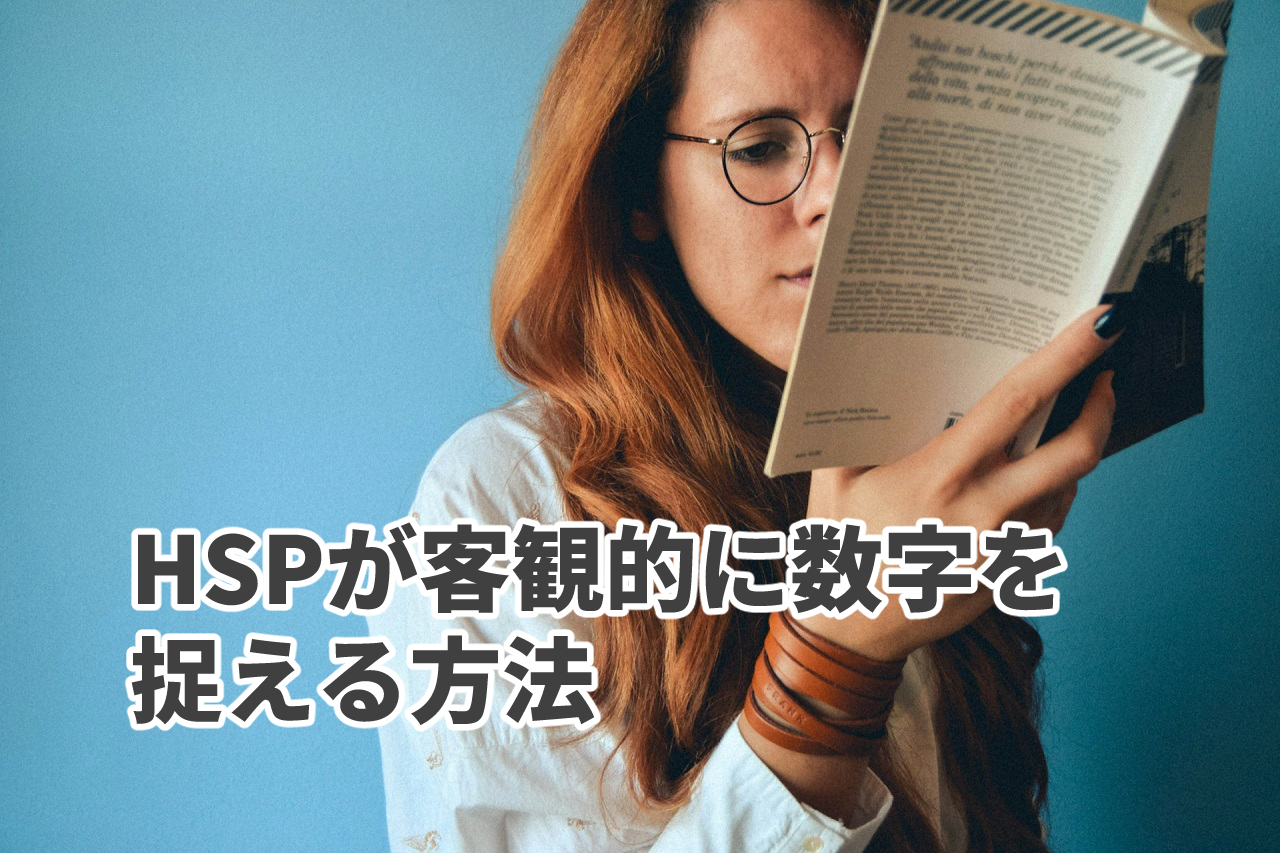


コメント