こんにちは✿
人間なら誰しもが持ってしまう「偏見」。
色んな事情を抱えた人が偏見の目で見られることが多く、HSPも例外ではありません。今日は私の観点から偏見について考えてみました。
というわけで、今回のブログのテーマは「HSPと偏見」です!
HSPとは?
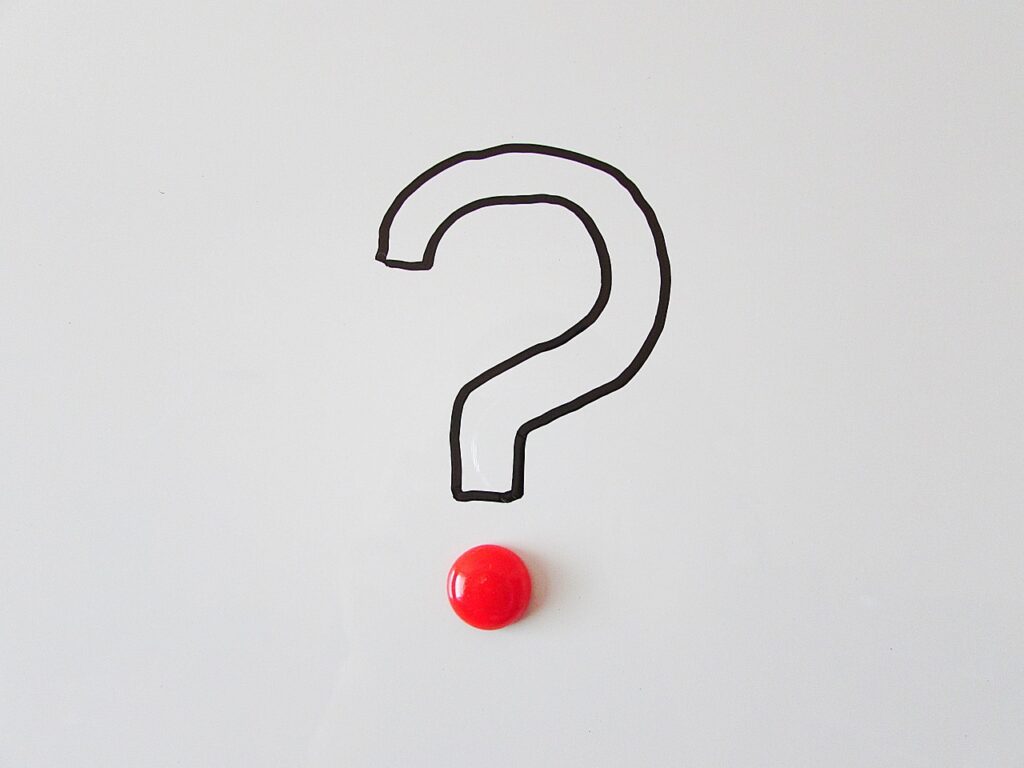
HSPは、Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)の略称です。なんだか病名のように聞こえるかもしれませんが、これは遺伝子的に生まれ持った気質のことで、アメリカの心理学者であるエレイン・N・アーロン博士が提唱した心理学的概念です。
生まれつき「非常に繊細な人」「敏感な人」「感受性が強い人」などという意味です。
全人口の約5人に1人はこのHSPに当てはまっているそうです。
HSPについてまとめた記事もあるので、興味がある方はぜひ。
HSP関連の本はこちらから。
HSPと偏見
偏見とは他人に対する先入観や偏った見方のことです。例えば、見た目や話し方、出身地など、さまざまな要因に基づいて、その人を特定の枠にはめてしまうことです。
偏見は誤った情報や固定観念に基づいていることが多く、個々の特性や能力を見落としてしまうことがあります。
HSPは偏見にどのように反応するか
HSPの感受性の高さは、日常生活や周囲の環境に対してより強く現れます。「音・光・匂い」などだけではなく、他人の感情にまで敏感に反応します。
そのため、偏見や差別的なことを言われたら心理的に大きなダメージを与えることも多いです。
相手がHSPに理解がない場合は傷つく場合がある
感受性の高いHSPが偏見を見聞きしてしまうと、その影響は特に大きくなります。
また、偏見を持つ人(HSPだろうが非HSPだろうが)が、HSPに対して理解がない場合、その偏見は感受性の高いHSPに対して、より大きなストレスや不安を与えてしまう可能性があります。
<相手>
非HSP
→
<自分>
HSP
<相手>
HSP
(感受性低め)
→
<自分>
HSP
(感受性高め)
要するに、HSPがHSPを傷つける可能性もあるということです。「HSPの発言はHSPを傷つけない」ということ自体が偏見になってしまいます。この例では「相手 → 自分」ですが、「自分 → 相手」になる場合も当然起こります。
HSPの中でも感受性の強弱があることを知っておく必要があると思います。
偏見と感受性にまつわる私のエピソード

私のエピソード
私は学生の頃から自分は「傷付きやすい」と思っていました。
例えば、非HSPならセンシティブには思えないような発言や行動に対しても、私は深く傷ついたり、不安になったりすることがありました。
クラスメイトが私のことを冗談半分で「泣き虫!」と呼んだとき、私の心には大きな痛みが走りました。そのとき彼らはただの冗談のつもりだったかもしれませんが、私にとってはその言葉が胸に深く突き刺さったと記憶しています。
「泣くこと」についてまとめた記事もあるので、興味がある方はぜひ。
偏見が感受性に与える影響
このような経験は、私の感受性に大きな影響を与えました。
私は他人の言葉や行動に対して過敏になり、自分自身を守るために周囲との距離を置くようになりました。
学校での生活は孤独感が増し、自分が異質であるという感覚が強くなりました。その結果、自分の感情を抑え込むことが多くなり、ストレスや不安が募るようになったのを覚えています。
自分自身の感受性と偏見にどう向き合ったか
このような状況に対処するため、私はまず自分の感受性を理解し、受け入れることから始めました。
自分がHSPであることを知り、その特性をポジティブに捉えるように努めました。
また、信頼できる友人や家族に自分の感情や経験を話すことで、少しずつ自分を取り戻していきました。そういう方々の理解やサポートは、私にとってはとても大きな力となりました。
偏見を克服するための対策

自分自身の感受性を理解する
偏見に対処するためには、まず自分自身の感受性をしっかりと理解することが重要です。

私はHSPなの。わかってる?私。
と自分自身に対して意識付けするということです。
私たち一人一人が持つ感受性は異なり、それを知ることで偏見に対する適切な対応ができるようになります。
HSPとして、自分がどのような状況や言葉に敏感に反応するのかを理解することが、自己ケアと精神的な安定に繋がります。
例えば、私は周囲のネガティブな言葉や態度に対して特に敏感であるため、そのような環境を避けることが重要だと思っています。さらに、ポジティブな環境を選び、自己肯定感を高めることも大切だと思います。
ネガティブな情報への対処法についてまとめた記事もあるので、興味がある方はぜひ。
他者の感受性にも目を向ける
自分だけでなく他者の感受性にも目を向ける必要があります。「自分だけがHSPなのではなく、今話している相手もHSPかもしれない」と意識付けするということです。
相手がどのように感じ、どのような背景を持っているかを理解しようとする姿勢が共感と理解を深めます。
例えば、友人や同僚が過度に反応しているように見える場合、その背景にある感受性を理解しようとすることが大切です。共感することで、互いの距離が縮まり、偏見による誤解が少なくなります。
共感の意識を持つことで、自分では気付いていない偏見に基づく行動や発言は減ってくると思います。
相手に誤解されにくくする方法についてまとめた記事もあるので、興味がある方はぜひ。
HSPコミュニティへの参加
感受性が高い人々がお互いに支え合うことができるHSPコミュニティに参加するのも対処法の一つとなります。
コミュニティでは、自分の感受性について話し合い、共感を得ることで偏見に対処する力を養えます。似たような経験を持つ人との考え方を聞くことがきっかけとなり、自分自身に合った対処法も見つけることもできます。
専門家からアドバイスを受ける
専門家(カウンセラー)のアドバイスを聞くのも対処法の一つとなります。
例えば、カウンセリングを通じて偏見に対する対処法が学べたり、日常生活に活かすための具合例を聞くことができたりします。
学ぶこと・行動すること
学ぶことや行動することも大切です。
新しい知識やスキルを習得し、偏見に対する対処法を学び続けることで、自分自身も強くなり、他人を適切にサポートできるようになります。例えば、心理学や社会学の勉強を通じて偏見のメカニズムを理解し、それに基づいて行動することができます。
また、いろいろなネットワーク(SNSやブログを含む)を通じて得た知識や経験を他者と共有し、自らが発信役になることも大切だと思います。
一朝一夕で偏見を完全に克服することは難しいですが、小さな一歩一歩が積み重なって大きな変化を生むことができると思います。
まとめ:感じ方は人それぞれ
というわけで、「HSPと偏見」についてブログで考えてみました。
- 自分の感受性を正しく理解する
- 他人の感受性のことも考える
- コミュニティに参加して人との繋がりを持つ
- 専門家からアドバイスを受ける
- 新しいことを学んだり、行動を起こす
「偏見」という言葉を簡単に語るのは難しく、重いテーマかもしれませんが、ときには考えないといけないことかなと思います。特に私はHSPというマイノリティな部分があるので、たまに深く考えてしまいます。
同じように偏見について考えている人で、この記事が参考になれれば嬉しいです。
ここまでブログを読んでくれてありがとうございます。
それでは✿
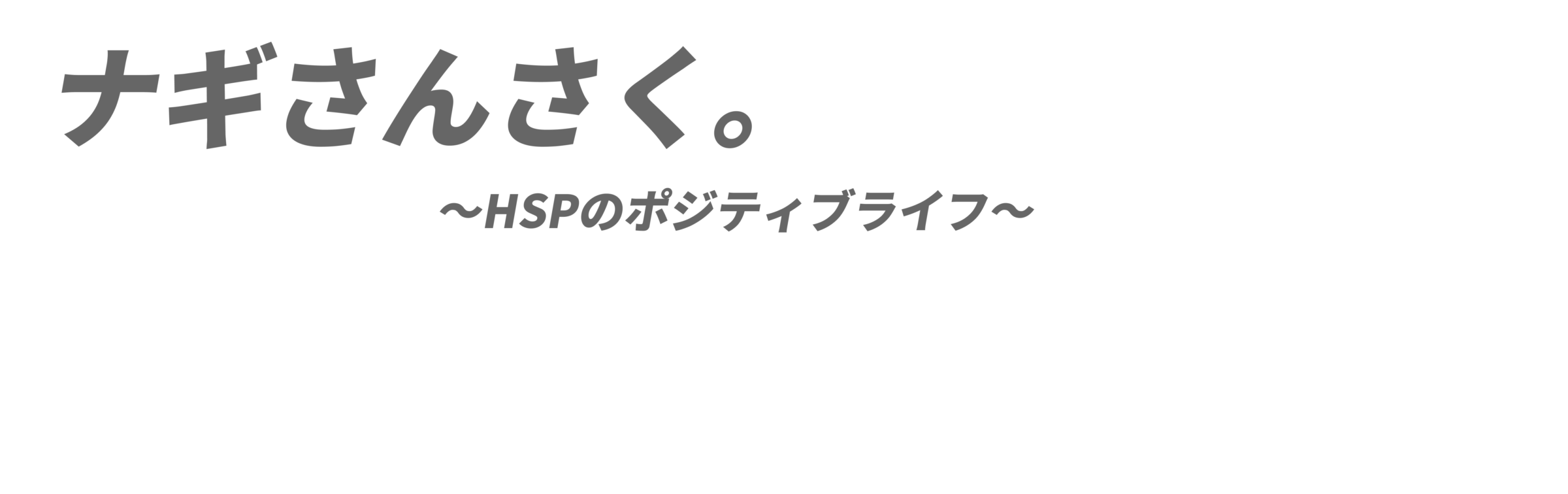







コメント