このテストは、あなたの「子ども時代のトラウマ」を見る自己診断です。
HSPの提唱者エレイン・N・アーロン博士の本『ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。』で登場したものです。
- 自分の子ども時代の経験が今の自分に影響しているかどうかを診断したい
- 本を読まずに診断したい
- 紙とペンを使いたくない
※この診断によってフラッシュバックが起こる可能性があります。診断する場合は、十分注意してください。
HSPとは?
HSPとは、Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)の略称であり、遺伝子的に生まれ持った気質のことです。この用語は、アメリカの心理学者エレイン・N・アーロン博士が提唱した心理学的概念です。
日本においては、有名な著書がきっかけで「繊細さん」などと呼ばれたりもしています。
HSPの人は、生まれつき
- 非常に繊細
- 敏感すぎる
- 感受性が強い
など、一般的な人よりも遥かに鋭い感覚を持っていて、HSPの傾向にある人の数は約5人に1人の割合だそうです。
2020年の日本の人口でいうと、
日本人口:約1億2,500万人
↓
HSPの傾向にある人:約2,500万人
という計算になり、その多くは自分がHSPであることを自覚し、自分の繊細すぎる気質に悩んでいると言われています。
なお、この記事は、そのHSP研究の第一人者であるアーロン博士の本「『ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。』で登場した「子ども時代のトラウマと今の自分の関連性」を分析するための自己診断です。
同書は「講談社」と「SB文庫」から出版されています。内容は同じなので、どちらを読んでも問題ないと思います。ちなみに、私は表紙がかわいい「講談社」の方を読みました。
この自己診断が、自分のことをより深く理解するきっかけになればと思っています。
この自己診断を受ける前に、有名なHSP診断テストを受けたことがない人には、次の記事をおすすめします。記事の中で「HSP診断テスト」ができ、紙とペンなしで、その診断結果がすぐにわかります。
この記事の自己診断を受けたことがある人は、ぜひ、次の診断も試してほしいです。どの診断も紙とペンなしで、診断結果まですぐにわかります。
このHSPに関する自己診断について
この診断をする前の注意事項として、アーロン博士は次のようなことを言っています。
- 比較的幸せで安定した子ども時代を送った人は、この査定はしなくてもよい
- (自分の子ども時代の幸運に感謝し)他者へ思いやりを培いたい人は、この査定するのもよい
- 既に、子ども時代の問題を解決している人は、この査定をやらなくてよい
- 査定をする人は、「ある程度のショックが来ること」を覚悟しておくように!
今回の自己診断は少し理解するのに時間がかかりそうだったので、色々なことを自分なりに変換してみました。
すぐに「自己診断」を始めたい方は、こちらから。
<「質問項目」の引用>
- エレイン・N・アーロン(1996年)著
- 冨田香里(2000年)訳
- 『ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。』講談社 P.275~277.
<質問(原文ママ)>
これから挙げるリストにそって進み、自分にあてはまる項目をチェックしよう。さらに五歳までの間に起こったことに☆印をつける。二歳以下に起こったことなら、二つ☆印をつける。もしその状況が長い間続いたのなら(「長い」とはどのくらいの長さなのかを自分なりに定義しよう)、チェックしたものや☆印をつけたものを〇で囲む。もしその出来事がいまだに自分の生活の影響を及ぼしていると思ったら、その項目もチェックする。チェックしたもの、☆印や〇をつけたものが、いちばん大きな問題の所在を教えてくれるはずだ。
『ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。』講談社 P.275~277.
診断しやすくするための配慮
各項目につき、13個の選択肢があり、選択肢の内容をそのまま書くと選択すること自体が難しくなるため、各選択肢のポイントとなるキーワード「いつ、その期間、今への影響」を改行して並べ、できるだけ直感的に選択しやすいようにしました。
選択できるチェックボックスは1個です。
「この項目については、”年齢は不明”、”長い”、”影響がある”」のようにキーワードのみを思い浮かべながら選択してみてください。
また、各項目あたりの行数が多くなるため、「項目の内容と選択肢」が瞬時にわかるようにセットにして枠で囲みました。(選択肢をチェックした後に回答が表示されます)
さらに、「全28個の項目についての選択肢」が瞬時にわかるように最後に一覧にまとめました。深堀り優先度の「★」の数が多い項目や気になる項目を探す時に使ってもらえればと思います。
<2023年12月14日 追記>
※不具合により上述のプログラムが動作しておりません。申し訳ございません。
<2023年12月18日 追記>
※プログラムの不具合を修正しました。
選択肢の意味
質問に対して、
- 年齢:その項目の状況がいつ始まったか(起こったか)
- 期間:起こった項目の期間はどのくらいか(「短い」「長い」は自分なりに定義する)
- 影響:その項目は今の生活に影響があるか
を答えてください。
例えば、
「年齢不明/短い期間/影響なし」
の選択肢は、
- その項目の状況がいつ始まったか(起こったか)は覚えていない
- 起こった項目の期間は短かった
- その項目は今の生活に影響がない
という意味です。
診断結果の深堀り優先度[★☆]の意味
「深堀り優先度」は点数ではありません。
診断内容が多くて、「どの項目が、どのような診断結果なのか、どこから検証していいか」がわかりにくくて迷ってしまうのを防ぐため、優先的に検証した方がいい項目を「マークするイメージ」で、瞬時にわかるようにしました。
「★」が多い項目が優先順位が高いです。
質疑に行く前に、最後に一言。
この質問を本で読んでいると、「この質問を紙とペンを使ってこなすのは大変だ」と思ったため、この記事を書きました。この内容をしっかりと消化するために活用してもらえたらうれしいです。
それでは、この先をどうぞ。
<注意事項>
- 選択した結果のみ選択肢の一覧に表示されます。結果を表示したい項目は必ず選択してください。
自己診断「子ども時代のトラウマ査定」の診断を始める
では、診断を始めます。
次の項目について、自分にあてはまる “ ○ ” を13個の選択肢の中から選択してお答えください。
※原文の質問を言い換えました。原文は前の段落のとおりです。
◆No.1:
両親はあなたの敏感さをいいものだと思っていなかった。しかも/または、うまく対処できなかった。
【No.1の回答】
◆No.2:
あなたは望まれない子供だった。
【No.2の回答】
◆No.3:
親や家族でもなく、心の温かい人でもない、何人もの養育者によって育てられた。
【No.3の回答】
◆No.4:
かなり過保護に育てられた。
【No.4の回答】
◆No.5:
自分で大丈夫だと思えること以上の、怖がっていることを無理にやらされた。
【No.5の回答】
◆No.6:
両親はあなたには肉体的/精神的におかしなところがあると思っていた。
【No.6の回答】
◆No.7:
両親や兄弟姉妹、隣人、学校の友達にいいように使われていたり、支配されていた。
【No.7の回答】
◆No.8:
性的虐待を受けた。
【No.8の回答】
◆No.9:
身体的虐待を受けた。
【No.9の回答】
◆No.10:
年中冷笑されたり、からかわれたり、怒鳴られたり、批判されたりといった「言葉による虐待」を受けた。あるいは、あなたの「自己イメージ」は、あらゆる意味で極端にネガティブな人によって作られてきた。
【No.10の回答】
◆No.11:
子供のころ、あまり注目してもらえなかった。あるいは、特別な業績や功績のためだけに注目してもらえた。
【No.11の回答】
◆No.12:
今までのパートナーや親しい人の中に、アルコール依存症や薬物依存症、精神病にかかっている人がいた。
【No.12の回答】
◆No.13:
親が病気だったり、身体障害を抱えていたため、あまり面倒を見てもらえなかった。
【No.13の回答】
◆No.14:
片親あるいは両親の身体的/感傷的な世話をしなければいけなかった。
【No.14の回答】
◆No.15:
精神保健の専門家が「ナルシスティック」「サディスティック」などと呼ぶ、一緒に生活しづらい親がいた。
【No.15の回答】
◆No.16:
学校や近所でいじめられていた。
【No.16の回答】
◆No.17:
慢性的な病気、けが、身体障害、貧困、天災、親が失業していた、大変なストレスがあったなど虐待以外の子供時代のトラウマがある。
【No.17の回答】
◆No.18:
あなたの育ってきた社会的環境では、いろいろなことをする機会を制限されていた。そして/または、家庭が貧しかったり、少数民族に属するなどの理由で「劣るもの」として扱われた。
【No.18の回答】
◆No.19:
自分ではコントロールできない大きな変化があった(引っ越し、死別、離婚、捨てられたなど)。
【No.19の回答】
◆No.20:
自分がいけないと思ったことについて強い罪悪感を感じたが、誰ともそれについて話ができなかった。
【No.20の回答】
◆No.21:
子供のころ、死にたいと思っていた。
【No.21の回答】
◆No.22:
子供のころに父親を失ったが(死亡、離婚など)その父親とはあまり親しくなかった。しかも/または、その父親はあなたの養育にあまり関わっていなかった。
【No.22の回答】
◆No.23:
子供のころに母親を失ったが(死亡、離婚など)その母親とはあまり親しくなかった。しかも/または、その母親はあなたの養育にあまり関わっていなかった。
【No.23の回答】
◆No.24:
右の二つの項目があてはまる場合、あなたは親が「自発的に自分を捨てた」とか、「個人的な理由で自分を拒絶した」と思っている。あるいは、あなたは自分の行動のせいで親を失ったと思っていた。
【No.24の回答】
◆No.25:
兄弟姉妹などの近い家族が死んだ、あるいはあなたから離れていった。
【No.25の回答】
◆No.26:
両親はいつもケンカをしていた。しかも/または、離婚してあなたのことで争った。
【No.26の回答】
◆No.27:
十代のころ、よく問題を起こしたり、自殺傾向があった。あるいはドラッグやアルコールを濫用していた。
【No.27の回答】
◆No.28:
十代のころ、あなたはいつも権力側(学校、警察など)と問題を起こしていた。
【No.28の回答】
【あなたの選択肢一覧】
お疲れさまでした。
まとめ:対処法について自分なりのパターンを見つけてみよう

皆さんの結果はいかがでしたか?
辛い質問続きで、しんどい思いをさせたらごめんなさい。
本の中でアーロン博士は、「自分なりにパターンを見つけてみよう」と言っています。具体的には次のような手順でパターンを探してみることを示されています。
- 選択肢によって恐怖が起こる
↓ - 自分の今までの歴史を振り返る
↓ - 自分のいいところを挙げる(才能・功績・他者の助けになった経験など)
↓ - 「3」と「診断項目のネガティブな点」を相殺する
↓ - 時間を置く(「散歩をするのもいいだろう」とアーロン博士は言っています)
↓ - 「3」や「 “ 診断項目のネガティブな点 ” に耐えてきた自分」を褒める
↓ - 今の自分には何が必要なのか自分なりに考える
アーロン博士はこのような具体例を示してくれています。もし、自分で対処できないくらいになってしまったらセラピーを検討することも勧められています。
もっと詳しく知りたい方は原書を読んでみるのがいいと思います。
また、トラウマ研究の世界的第一人者ベッセル・ヴァン・デア・コーク博士の著書「身体はトラウマを記録する 脳・心・体のつながりと回復のための手法」の記事もまとめています。
興味がある方は読んでみてください。
こちらは「トラウマを克服する方法」を中心にまとめています。
さらに、子ども期の逆境体験について研究する専門家によって解説された著書「ACEサバイバー 子ども期の逆境に苦しむ人々」の記事もまとめています。
興味がある方は読んでみてください。
今回の自己診断は少し理解するのに時間がかかりそうだったので、いろいろなことを自分なりに変換して書いてみました。
少しでも興味が沸いた人は、次の記事も読んでもらえると嬉しいです
ここまで読んでくれてありがとうございます。
それでは✿
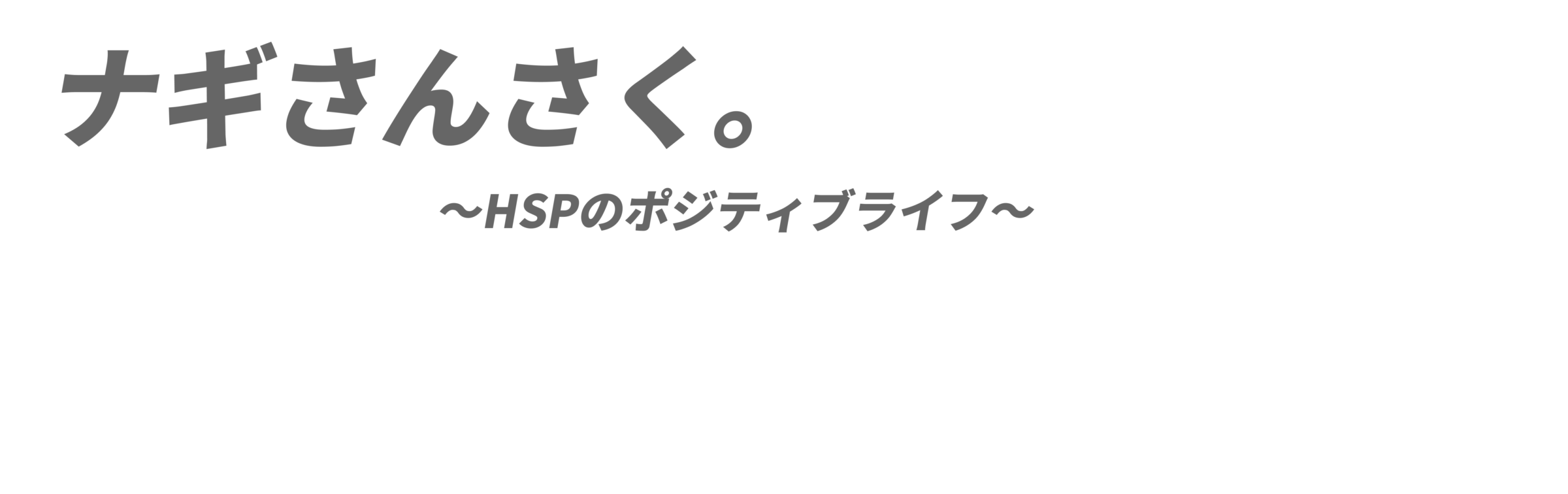
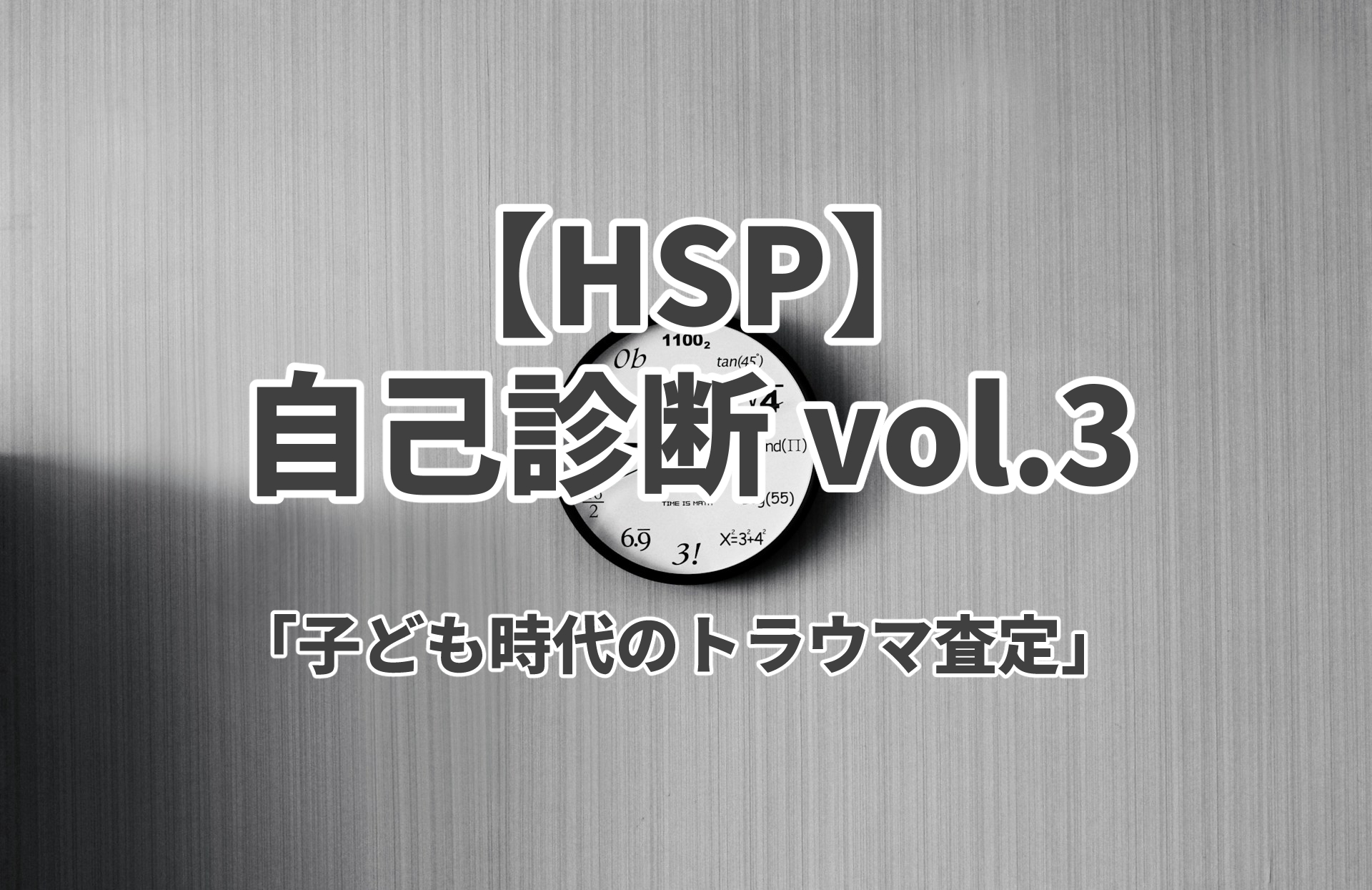








コメント