こんにちは✿
今日は、「トラウマを克服する方法」の1つでもある「演劇」について書こうと思います。
演劇と言ってもトラウマに効果的なのは、演劇を観るではなく、「演劇をする」方を指します。
このテーマを聞くと、

演劇がトラウマに効くってどういうこと?

演劇とトラウマに何の関係があるの?
などの疑問が浮かぶかと思いますが、できるだけ深掘りして解説していきます。
この記事のほとんどは以下の本から引用させていただいています。
長年トラウマの研究をしている権威ある方が書かれた本なので、大変参考になりました。
興味が湧いた方はぜひ!
トラウマとは?
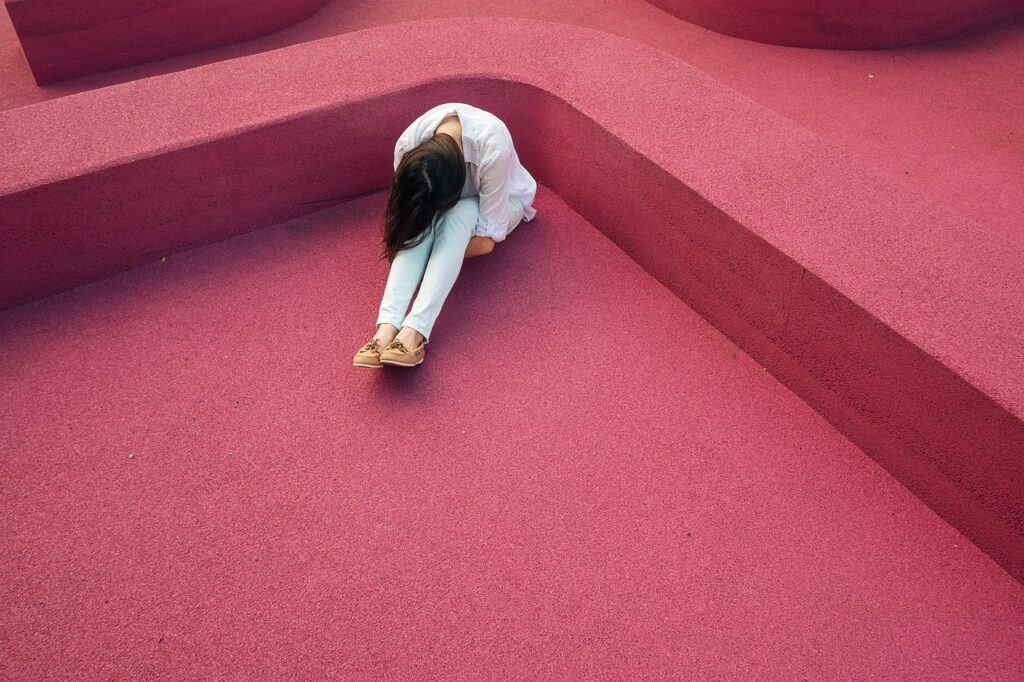
トラウマとは、心に深い傷を残す出来事や経験を指します。
人生において、予測不可能で強烈な出来事が、時には心の奥深くに刻み込まれ、それがトラウマを生む原因となります。通常の日常生活で経験するストレスや困難な状況とは異なり、トラウマは異常なほどの精神的な衝撃を伴います。
トラウマは様々な形で現れ、
- 事故
- 虐待
- 災害
- 戦争
などの極端な状況が挙げられます。
同じ出来事でも人それぞれ異なる影響を受けることがあり、子供時代の虐待や家庭内の問題、そして心の中で解決しきれない葛藤なども、トラウマの源となり得ます。
これらの出来事がトラウマとして残ると、その影響力は大きく、しばしばそれに苦しめられることになります。トラウマの影響は直ちに表れないこともあり、時には数年経ってから現れることがあります。そのため、トラウマに気づきにくく、放置されがちな傾向があります。
トラウマが心に残る主な要因は、出来事が予測不可能であり、かつ個人にとって脅威的であると感じられることです。この心の傷は、適切なサポートや処置なしには、長期間にわたって影響を与え続ける可能性があります。
トラウマのより詳しいことは、こちらの記事に書いてあります。
なぜ演劇をするとトラウマケアになるのか?

ここからは、「なぜ演劇がトラウマケアになるのか」を解説していきます。
理由は主に3つあります。
- 自分の主体性を取り戻せる
- コミュニケーション能力が養われる
- 達成感を味わえる
自分の主体性を取り戻せる
トラウマを負った人は、トラウマによって自己を見失ってしまいがちです。
自分がどのように感じているか、どういう気持ちなのかなど自分の内部の声を感知するのが苦手になってしまい、感情を上手く表現できなくなる傾向があります。
しかし、演劇では舞台の上で感情を声や体で表現しなければならず、観客にストーリーを伝えなくてはなりません。感情を表現する演劇は、いわば「感情を上手く表現している人」の体験ができることになります。
主体感覚、つまり自分がどのぐらい主導権を握っているのかという感覚は、自分と体やそのリズムとの関係で決まる。(中略)演技とは、自分の体を使い、人生において自分の場所を確保する経験なのだ。
『身体はトラウマを記録する 脳・心・体のつながりと回復のための手法 P.552~P.553』
物事を深く感じることや様々な葛藤(自分の心の葛藤、人間関係の葛藤、社会的な葛藤など)を恐れるトラウマサバイバー(トラウマを負った人)にとって演劇は、自分の内部を探り、真実を伝えようとする方法を探る経験になりえます。
コミュニケーション能力が養われる

トラウマを負った人は、周囲に合わせることが苦手です。
しかし、演劇をする上では、まわりとのコミュニケーションは切り離せませんし、一人芝居でない限り、他者との協調性は欠かせません。
そんな中で、トラウマサバイバーは、演劇をしていくうちに相手にどんな影響があるか考えるようになり、自然と他者の存在を意識するようになります。
こうした経験が、新しい人間関係を築くきっかけにもなります。
達成感を味わえる

同じ目的を持った集団の中で、何か大きなことを成し遂げる「演劇」という経験は、非常に良い達成感が味わえます。
トラウマを負った人は、「自分は大したことはできない」と思い込んでいる人が多いですが、周囲と協力し合って目の前の課題に立ち向かう経験によって、それが自己成長にも繋がっていきます。
このように集団で熱心に物事に取り組むと、子供たちは協働し、妥協し、目前の課題に意識を集中し続けざるをえなくなる。張り詰めた雰囲気になることが多いが、子供たちはやりとおす。コーチや監督の敬意を勝ち取りたい、チームをがっかりさせたくないと願っているからだ。こうした気持ちはみな、気まぐれな虐待にさらされるときの無力感や、ネグレクトされるときの、見向きもされていないという感覚、トラウマがもたらす救いようのない孤独感とは正反対だ。
『身体はトラウマを記録する 脳・心・体のつながりと回復のための手法 P.596』
演劇によって立ち直った人たち
本書の中でも実際、演劇をすることによって明らかな変化が見られた人々がいると紹介しています。
ある芸術団体が運営する演劇グループに、トラウマを負った10代の子どもたちを参加させました。
しかし、その子どもたちは、かなり攻撃的で常に不機嫌な態度でいる上、何度も過激な暴力事件を経験していたそうです。
さらに、誰かが身の危険にさらされたときには、みんなは決まって攻撃側に回り、他人も自分も弱さを見せるのが許せなく、思いやりの気持ちなどは全くありませんでした。
そんな子どもたちは、演劇プログラムに取り組んでいくうちに徐々に変化が見られ、弱さを晒す役を自ら買って出る子まで現れ、プログラムが終わる頃には、子どもたちが自分で描いた絵を関係者たちに送り、感謝の気持ちを示したと言います。
演劇プログラムを開始した当初は緊張のあまり凍り付いてしまったり、逃げ出してしまったりする人がいたりと、かなり苦戦しますが、仲間たちとひとつの課題に取り込むうちに、何かしらの良い変化が芽生えるきっかけになり、トラウマを乗り越える力を取り戻せているのではないかと本書の中で考察されています。
本書で書かれている他の「トラウマを克服する方法」は、こちらの記事に書いてあります。
まとめ:演劇は自己成長とトラウマ克服につながる
今回は「トラウマと演劇」の関係性についてまとめました。
トラウマを負った人は自身の感情に蓋をしてしまいがちですが、演劇はまさしくその逆で感情を表現する場です。
演劇の体験が、自分の内部感覚の再発見に繋がり、さらにまわりとのコミュニケーションの場にもなりえるので、トラウマ回復にはかなり効果的だという結論でした。
引用している本書の目次を読んだときは、トラウマと演劇の組み合わせは意外だらけでしたが、トラウマの詳しい仕組みを知ったら非常に納得できました。
「生きづらさ」について考えがちな私からしたら、今回のテーマもすごく興味深いもので、またひとつ勉強になった気がします。
というわけで、ここまで読んでくれてありがとうございます。
それでは✿
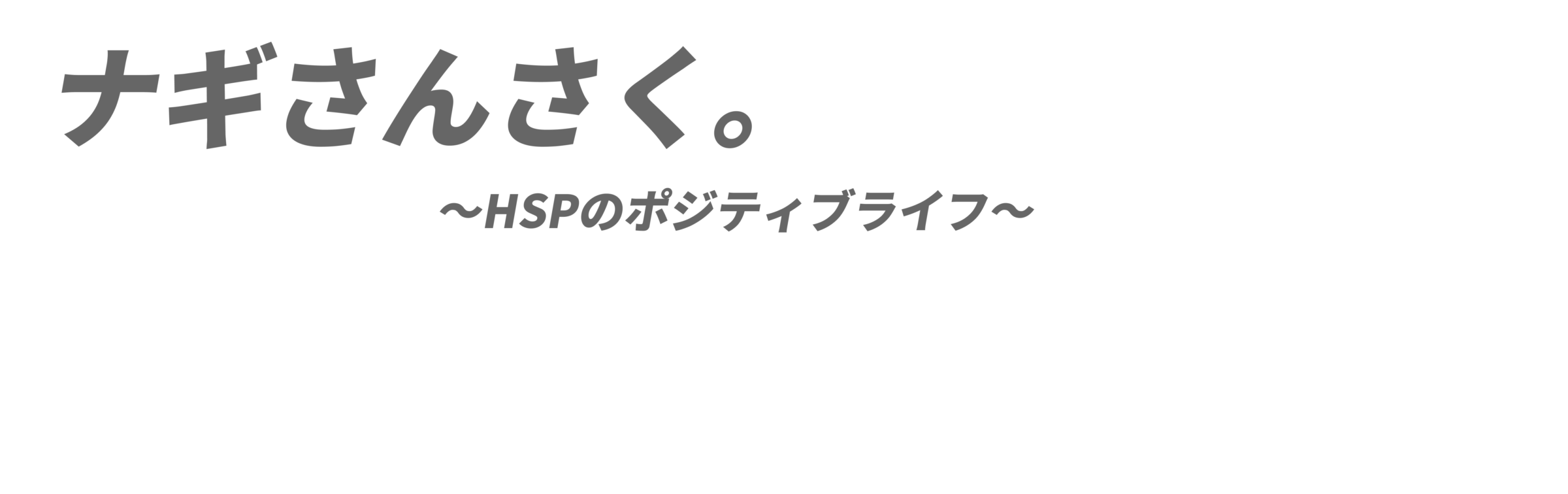
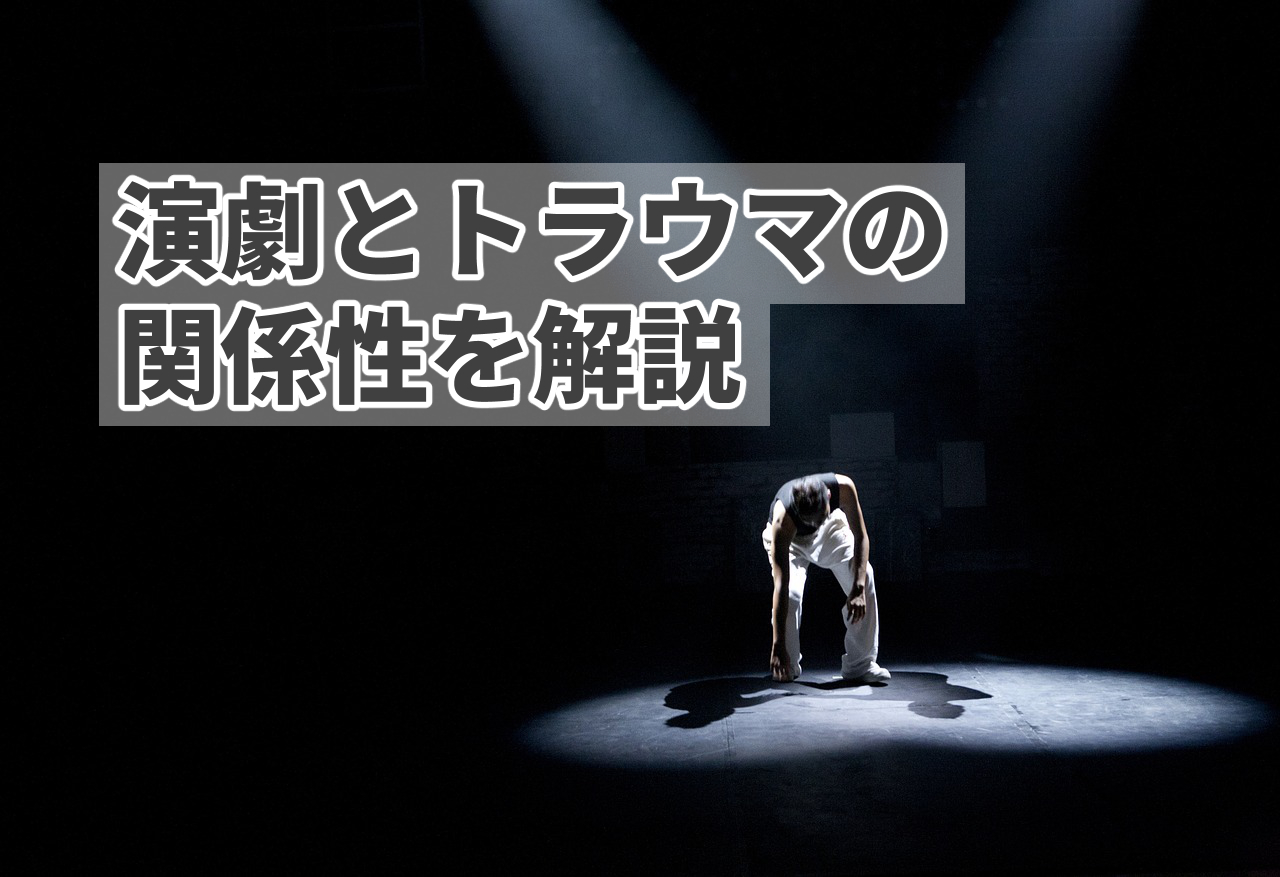



コメント